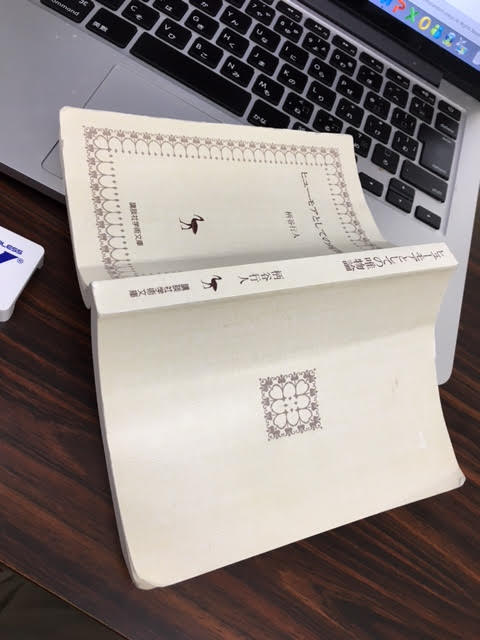『ヒューモアとしての唯物論』
柄谷行人著 (講談社学術文庫 1999年)
「美味しい食べ物が好き」とか、「美しい自然が好き」とかいう人は少なからずいる、というか、大抵の人はそうした個人の嗜好を誰にとっても自然な当たり前なものと認識しているのだろう。そして、その人たちは「優しい人に出会いたい」、「おしゃれな服が欲しい」などということも、当たり前のことと考えているかもしれない。この「だろう」とか「かもしれない」という書き方から察しがつくように、「美味しい食べ物」「美しい自然」「優しい人」「おしゃれな服」というものに、僕は懐疑的だ。
例えば、「美味しい食べ物」と言った場合、その「美味しい」とは、言葉を発する本人にとっては特に根拠のない個人の主観であり、かつ、その主観というのも所属する地域の食文化や育った家庭の環境などといった「構造」によって培われた相対的で暫定的なものにすぎない。簡単に言えば、味覚とは「慣れ」にすぎないのではないか。だから、僕は「美味しい」なんて、あやふやなものを信じることができない。いわゆる「グルメ」というのがどうにも苦手なのは、「美味しい」などという、ひどく脆弱な価値基準のうえに成り立った遊びに思えるからだ。もし、僕が食べ物に特別な「価値」を見出そうとするなら、「美味しい/不味い」といった形而下のレベルを越えたものでなければならない(なので、「ヴィーガン」や「ロカヴォア」といった食に対する「コンセプチュアル」なアプローチは、その実践はともかく、共感はする)。
というより、そもそも「美味しい/不味い」以前に、「食べ物」とは何なのか。動植物たちが、われわれ人間の「食べ物」に姿を変えるのは、いつ、どの時点でのことなのか。それもまた、当該地域の文化や歴史といった「構造」に立脚するものなのだろうか。だとしたら、何をもって、それを「食べ物」とするのか、まず「食べ物」という概念を明確に定義付けなければならないのではないか…。
とかいうのは、半分冗談で半分本気。というのも、こうしたひどく抽象的なものの考え方というか、ものごとの捉え方を僕は子供の頃からしていて、「美味しい」も「楽しい」も、それをそう感じさせる因果関係がその背後にあるというようなことを直感的に感じていたのだと思う。なので、10代で柄谷行人の著作に出会い、すぐに「ハマった」のは、ある種の必然であったと感じる(もちろん、「ニューアカ・ブーム」という時代背景という「構造」の影響も大いにある)。
以降、30年近く、僕は柄谷行人の本を常に手元に置いている。
「日本において、『風景』は明治20年代に発見された」
「ナショナリズムは近代小説の成立とともに形成された」
とくに起源を持つわけでもない、人間にとってごく自然の、当たり前の事柄だと誰もが信じてきたものが、実は歴史の一時期に特定の因果関係のもとで構造的に作りだされたものであると解き明かす。こうした、柄谷行人の一連の著作は、それが文芸評論であっても、あるいは難解な哲学的思索を述べたものであっても、僕にとっては最高級のミステリ小説なのである、と言ったら顰蹙を買うだろうか。
柄谷行人の本であったらなんでもいいのだけれど、今日、いま、手元にあるのは『ヒューモアとしての唯物論』。なので、これを紹介します。