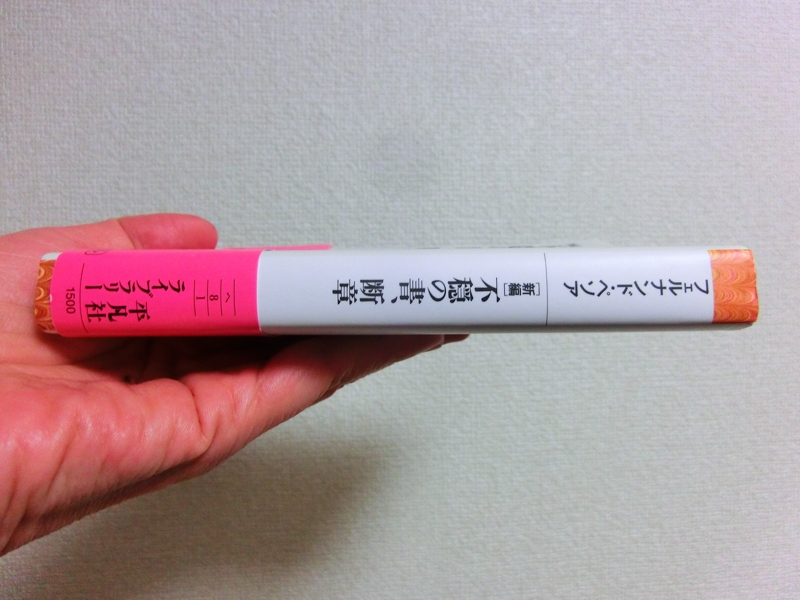『不穏の書、断章』フェルナンド・ペソア
(平凡社ライブラリー 2013年)
断片や断章というものに強く誘惑される。はじまりもおわりもなく、ペンが動くにまかせて書きはじめられ、ペンの動きが停まったところで途切れているようなもの。言葉が結晶となって差し出されているもの。そして永遠に未完のもの。
フェルナンド・ペソアは1888年にポルトガルのリスボンで生まれて、1935年にリスボンで死んだ。死んだあとにはトランク一杯の原稿が残された。自分のなかの他者を具体的な存在として何人も作り上げ、それぞれの名前で書かれた詩や断章、タイプしたものや手書きの原稿がぎっしりと詰まっていたという。やがてそれらの原稿が整理され、まとめられると、ペソアはポルトガルの国民的詩人になった。それが日本語に訳され、さらに独自に編集されたのが『不穏の書、断章』というコンパクトな一冊だ。「断章」には1から141、「不穏の書」には1から126とナンバーがつけられているけれど、順を追って読む必要はない。どこからどのように読んでもいい。たとえば、ぱらりと開いたページには。
世界が作られているのは、われわれがそれについて考えるためではない。
(考えるとは、眼の病気だ)
そうではなくて、われわれがそれを眺め、それに賛成するためなのだ。
「考えるとは、眼の病気だ」なんて何度読んでもすごい。ペソアにとって、考えずに見ることは重要なテーマのひとつであり、それにについての断章はたくさんある。「見ているつもりがまるっきりわからずで、ぼーっとしているときが、いちばんはっきりと見える」というような、おそらく誰もがぼんやりと感じている小さなことを、なにげないままにはっきりと書いてあるものが好きだ。
ペソアはフランツ・カフカとほぼ同時代の人だ。昼間は簿記係として働き、夜になると自分の部屋で書きたいことだけを書いたという生活も似ているし、生前にほとんど著書を残さず無名だったところも同じだ。でも、リスボンの明るさはプラハとは違う性質を持っている。どちらも行ったことはないが、「あらゆる波止場は、石の郷愁(サウダーデ)」という一行を読めば、それはよくわかる。
アントニオ・タブッキはペソアの研究者でもあって、『フェルナンド・ペソア最後の三日間』という小説を書いた。ペソアが作った三人の重要な存在が、病院で死にかけているペソアをそれぞれ訪ねてくる。またポルトガルの作家ジョゼ・サラマーゴには『リカルド・レイスの死の年』という長編小説がある。リカルド・レイスはペソアが作った三人の重要人物のうちのひとりで、リオデジャネイロで暮らす医者だ。彼がペソアの訃報をきいてブラジルから船でポルトガルに着いたところから長い物語は始まる。ペソアは小説を書かなかった(と思う)が、彼の詩には小説家を刺激する構造と新しさがあるのだ。『不穏の書、断章』の訳編者澤田直は「ペソア・ウイルス」と呼んでいる。
ペソア・ウイルスに軽く感染している私は、いまのところはこの本に、以下のペソアの詩の好きな一節を加えて、自分だけの一冊としている。こうしてペソアのことを書いているうちに、自分で編集して新しい一冊を作りたいと思い始めた。ウイルスが増殖しているのかもしれない。
ひとは見捨てられて生きている
真理も 懐疑も 導師もない
人生はよい 酒はさらによい
愛はよい 眠ることはさらによい