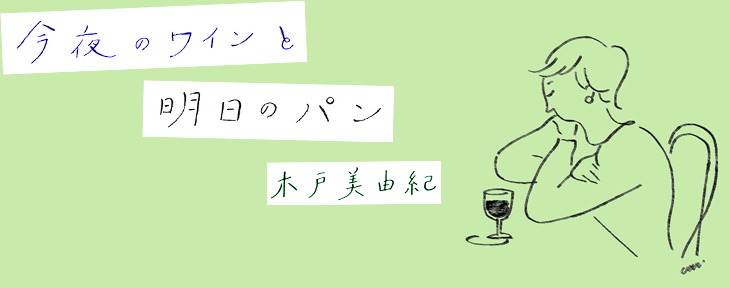
第二回 炊き込みご飯をタッパーに詰めて
「お仕事は何をされているのですか?」と聞かれると、「ライターとコーディネーターをしています」と答える。 ライターは、フランスやヨーロッパで取材した記事を日本の雑誌に書く仕事。コーディネーターは、雑誌やテレビ、ブランドのカタログや写真集などの撮影準備と現場の立会い。撮影後のショッピングや食事の同行も仕事のうちだ。
この仕事への扉を開いてくれたのは、コーディネーターのチカさんだ。パリで暮らし始めて2年目の2003年、語学学校に通いながら仕事を探していたところ、友人がチカさんを紹介してくれた。聞くとベテランのコーディネーターで、日本の広告や雑誌の撮影を数多く手がけているという。
アシスタントの面接は、5月半ばの快晴の日だった。 待ち合わせ場所はマレ地区の著名なダンスセンターのそばにある小さなカフェ。前夜から「こんな質問を受けたらこう答えよう」と頭の中で練習をし、準備万端で臨んだ。緊張しつつ、約束の10分前にカフェへ到着し、テラスに座ってコーヒーを頼んだ。ところが、コーヒーを飲み終わっても彼女は現れない。お替わりを頼もうか迷っていたら、抜けるような青空を背景に、腰まであるウェーブヘアをふわりふわりと揺らし、「ごめん、ごめん」と言いながらチカさんがやって来た。大きなサングラスに真っ赤な口紅、白いシャツの首元にはプッチのスカーフ。ほっそりとした脚にスリムジーンズがよく似合っている。
用意した職務経歴書、以前勤めた出版社で手がけた記事をまとめたファイルを渡すと、チカさんは、黙って真剣にファイルを見てくれた。時間にしたら10分ほどだったのかもしれない。いたたまれない気持ちになり、喉がからからになったが、コーヒーはさっき飲み干してしまった。チカさんが口を開くまで、私は彼女の全ての指にはめられた大きな指輪を眺めていた。 いくつか質問を受け、緊張が解けぬうちに面接は終わった。「アシスタントが必要な際は連絡するね」と言って、彼女はカフェの2軒先にある事務所へと去っていった。
6月になり、語学学校が長い夏休みに入ると、チカさんから連絡が入った。ファッション雑誌「GINZA」のパリ特集の準備と撮影を手伝ってほしいと言う。「GINZA」は、日本にいた頃よく読んでいた雑誌だ。撮影に立ち会えるのが嬉しかった。 その時は編集者が2人、著名なスタイリストが1人、日本からパリにやって来た。チーム編成は、モデル撮影などを行うファッション班が1チーム、「スタイリストが案内するパリガイド」の取材班が2チーム。私はファッション班の撮影アシスタント。他にライターとして取材班にも参加した。撮影では、ロケバスに置く飲み物やお菓子の準備をしたり、お弁当の買い出しに行ったり、そんな雑用をパリでするのも新鮮で楽しかった。 その仕事は10日ほど続いた。スタッフが帰国した翌日は、チカさんの自宅に撮影で使った荷物を運んだ。昼時だったので、チカさんと一緒にご飯を作った。鍋で白米を炊き、おかずは焼き鮭と、お酒を少し入れただし巻き卵、小ねぎを散らした豆腐のお味噌汁。シンプルな食事が、撮影続きで疲れた体に染みた。「家では毎日和食。フランス人のパートナーは和食を食べないから、同じ食材でフランス料理を作るのよ」というチカさんの言葉に、2倍の手間をかけて偉いなあ、と感心したものだ。
アシスタント時代は2年ほど続いただろうか。エネルギッシュなチカさんと仕事をするのは楽しかった。その間に多くの編集者を紹介してもらい、やがて取材や撮影コーディネートの仕事を直接いただくようになって独立したが、その後もチカさんの仕事を手伝ったり、食事をしたりと付き合いは続いた。
彼女が脚の関節を痛めたのは、2014年頃のことだったと思う。手術のために、パリから車で30分強の場所にある病院、アメリカンホスピタルに入院することになった。
手術の数日後に「病院食がフランス料理で辛い。和食を持ってきてほしい」と電話が入った。チカさんに恩返しができるチャンスだ。私は、マルシェへ足を運んで新鮮な食材を入手し、台所に立った。
まずは日本から持ってきたお米を研いで、細かく切った鶏肉、干し椎茸、キノコやニンジン、調味料と一緒に炊飯器へ。次に、大きなサーモンに塩を振り、ガスオーブンで焦げ目がつくまで焼く。そして京都出身のチカさんの口に合うよう、上等な昆布と鰹節をたっぷり使った関西風の出汁を取る。その出汁と薄口醤油を使って、だし巻き卵、ほうれん草のおひたし、ひじき煮を作った。弁当箱をがないので、1つのタッパーにおかず、もう1つのタッパーに炊き込みご飯を詰め、私は愛車ルノー・クリオを運転して、病院に向かった。
病室に入ると、チカさんの顔色はあまり良くなかった。それでもお弁当を渡すと、すぐに包みを開けて、まずは炊き込みご飯、それからおかずに箸をつけ、久々の醤油味と日本米が嬉しい、とにっこりした。
アメリカンホスピタルは、フランスでも有数の高級医療施設で、駐在員や外交官などが通う場所だ。チカさんの部屋は個室で、備え付けのテレビは海外向けの日系放送が受信できた。日本のテレビ番組を見ながら、二人でぼんやりしていると、ホテルマンのような制服に、白い布手袋をはめた女性が夕飯を運んできた。大きなトレイの上には、フードカバーがかかった陶器の皿が3つ載っている。そしてグレーのペーパーナプキンに包まれた、ナイフ、フォーク、スプーン、デザートスプーンなどのシルバー類。足付きのグラス。まるでルームサービスのようだ。
そのトレイを見たとき、突然、学生時代の記憶が蘇った。授業中に、ゼミの先生が言ったのだ。
「パリを旅行するなら、海外旅行保険に必ず入るように。調子が悪くなったら、ホテル並みの設備のアメリカンホスピタルに無料で入院できます。そしてルームサービスのようなフランス料理の病院食が食べられます」
先生の教え通り、私は渡仏時には毎回必ず海外旅行保険に加入していた。「いつかアメリカンホスピタルに入院できるかな」と淡い期待を抱いて。しかしその機会は一度も訪れていない。
きっと羨ましそうな顔でトレイを眺めていたのだろう。チカさんが「これを食べて行ったら」と薦めてくれた。
「えっ、いいんですか、悪いなあ」
多少の遠慮を見せつつ、トレイを引き寄せ、カバーを開けた。前菜は魚のテリーヌ。メインはチキンのクリーム煮、タイ米と野菜添え。デザートはチョコレートのタルトだ。魚と海老のテリーヌは白とオレンジ色の組み合わせが美しく、チキンにはたっぷりとクリームソースがかかっている。これが長年夢見た食事…と感激しつつ、少しの間、手をつけずに鑑賞した。それから、前菜のテリーヌを小さく切って口に入れた。滑らかな舌触り! しかし魚介の香りがしない。味は薄く、塩味のないはんぺんを食べているようだ。次はメインの鶏肉。一口分を切り、クリームソースをよく絡めて口に入れる。脂肪分が少ないクリームを使っているのだろう、ソースの口当たりは軽い。だがこれも塩味が足りず、味が薄ぼんやりしている。肉を噛み締めると、火の入れすぎなのか、ボソボソして固く、よく噛まないと飲み込むのも辛い。前菜とメインをやっとの思いで食べ終えたが、デザートに手をつける気にならず、持ち帰ることにした。
病室を後にすると外はもう暗かった。憧れの病院食は期待した通りのものではなかったけれど、学生時代からの夢が叶ったのは本当に嬉しかった。車のエンジンをかけると、ラジオから私の好きなジャズの曲が流れてきた。アート・ブレイキー&ザ・ダブル・シックス・オブ・パリの「Tin Tin Deo」だ。
鼻歌を歌いながらパリへと車を走らせる。その旋律に合わせるように、オレンジ色の明かりが灯る街の景色が、後ろへ、後ろへと流れていった。
(イラスト/題字 山本アマネ)