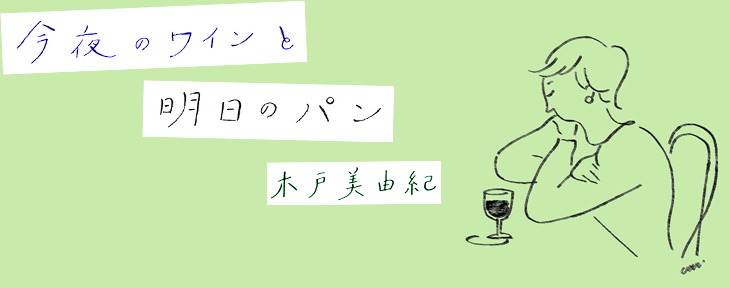
第一回 パンとバターとジャンボンがあれば
1年間の滞在のつもりだったのに、パリに住んでから20年が経とうとしている。 2001年12月、それまで勤めていた会社を辞め、その3週間後、語学留学を目的 に渡仏した。パリを選んだのは、フランス人と結婚した大学の先輩のお宅に、ホームステイをさせてもらえることになったからだ。
パリの緯度は北海道の稚内よりも上にあるというから、寒さは覚悟をしていたけれど、1月の気候は想像以上に辛かった。空は厚い雲に覆われ、日中でも暗い。その年は雨が多く、小雨に煙る街を歩いては、うら寂しい気持ちになったものだ。冬の東京の、清々しい青空が恋しかった。
天気だけではなく、生活面でも辛いことは多かった。東京でフランス語は勉強したものの、語彙も表現力も乏しく、ものを買うこと、荷物を送ること、携帯電話の契約、日常のあらゆることを試練に感じた。店員の説明が理解できず、何度も聞き返すと、気の短いフランス人はいらつき、ヒステリーを起こす。そんな対応を受けるたびに傷つき、意気消沈し、1年の留学期間を切り上げて帰国しようかな、とも考えた。
2月半ば、学生ビザの手続きで、パリ警視庁内にある移民局を訪れる機会があった。 受付で書類を提出して廊下の椅子に座り、順番を待っていると、小柄でほっそりしたアジア人の女の子が隣に腰を下ろした。手に握りしめたパスポートは日本のものだ。親近感を覚えながら、横目で観察する。色白で目が大きい彼女は、たいへん緊張していた。その様子から、小動物を思い出した。そう、リスか小鹿みたいだ。
しばらく経つと名前を呼ばれ、3人が部屋に入った。小鹿も一緒だ。手続きはあっという間に終わった。移民局の係員はパスポートに学生ビザを貼り、このあと配布する用紙を持参の上、3月の指定日に検診センターで健康診断を受けるように、と言った。
小鹿を見ると、不安そうに目をしばしばさせている。
「指定日に検診センターへ健康診断に行くように、だって」
と小声で訳すと、驚いたのであろう、青白かった頬がさっと染まり、大きな目は、さらに大きく見開かれた。手続きが済み、移民局の事務室を出ると、小鹿が駆け寄ってきた。
「私、パリに来たばかりで、まったくフランス語がわからないんです。健康診断、一緒に行ってもいいですか」
もちろん、と答えて名前と携帯番号を交換し、その日は別れた。
彼女の名はYちゃん。両親は原宿で美容院を経営。彼女もヘアスタイリストを目指して、美容専門学校に留学した。住まいはパリ左岸のオデオン駅のそばで、日本人の女性とルームシェアをしている。検診センターはパリ郊外にあり、そこに向かうRERという高速電車の車内で、そんな話を聞いた。
検診センターに着くと、着衣で靴を履いたまま、身長と体重を測り、視力や聴力の検査をした。最後にお医者さんの問診があり、今まで打ったワクチンの種類を聞かれ、フランスで摂取すべきワクチンのリストをもらった。この検診でフランス滞在に関する公的手続きは終わる。心底ほっとした。
検診センターから駅までバスもあったが、徒歩でも15分で着く。3月も終わりに近づいたこの日は、上着がいらないほど暖かかった。私たちはコートを片手にぶら下げて、駅まで続く川沿いの道をゆっくり歩いた。午後の光を受けて川面がきらきら輝き、眩しいほどだった。
それからしばらく経ち、4月も半ばを過ぎた頃に、Yちゃんから電話が入った。
「日曜日に、うちでブランチでもいかがですか」
そこで、メイクアップアーティストを目指している友人、J子も誘い、オデオンへ向かった。
Yちゃんのアパルトマンは、駅から近く、観光客向けのレストランが並ぶ小道沿いにあった。部屋は最上階で、エレベーターはない。螺旋階段を上り、7階にたどり着いた時は息が上がっていた。アパルトマンの間取りは、広々としたダイニング兼リビング、それに寝室 がひとつ。リビングには大きな窓が4つあり、そこからさんさんと日が差して、室内は暑いくらいだった。YちゃんのシェアメイトのRちゃんは、綾瀬はるか似の華やかな美人なのに、性格は三枚目。私たちはすぐに打ち解けた。
YちゃんとRちゃんは、さまざまな種類のバゲットを用意してもてなしてくれた。細長くて、皮も身も軽い、〝バゲット・パリジャン”。それよりも皮がやや厚く、中身がみっちりした〝トラディション(小麦粉、水、塩、酵母といった規定の材料を用いて、長時間発酵させたもの)”、麻の実付き、ゴマ付きが1本ずつ。それにバター、ジャム、リエット、ハム、ピクルス、チーズが数種類と、みんなで持ち寄ったワインが4本。
バゲットを手でちぎって、バターをたっぷり塗り、そこにジャンボン・ド・パリと呼ばれるハム、ピクルスを挟む。バゲットの皮は香ばしくパリパリで、身はふわりと柔らかい。パンの甘み、バターのコク、ハムの塩分とピクルスの酸味が絶妙に調和して、これをつまみにワインがいくらでも飲める。食卓に並ぶのは、パンとありふれた食材だけ。それを組み合わせて、さまざまな味を楽しめるのは意外だった。
「蜂蜜と、塩気が強い青カビチーズは相性がいいねえ」
「バターを厚めに塗ったパンとカマンベールも、クリーミーで美味しいよ」
などと、気に入った味を薦めたり、薦められたりするのも愉快だ。
ワインが進むと、剽軽者のJ子が冗談を連発し始め、私たちは食べ、飲み、笑い続けた。リビングの窓は大きく開け放たれ、その向こうは青空だ。部屋を吹き抜ける風が、なんとも心地よい。
夕方になると、1階のレストランから、クラシックギターの演奏が聞こえてきた。少しもの悲しいギターの曲を聴きながら、窓枠に座ったり、もたれたりして、4人ともしばらく黙った。空は少しずつ、茜色から藍色に変わっていく。
そう、確かこの時、パリに住んでよかった、と初めて思ったのだ。さらに「1年は短すぎるから、もう少し長く住んでもいいかな」とも。
それから5年、10年、15年が経ち、節目のたびに、そろそろパリの住まいを引き払って東京で頑張ろう、と思いながら、決心がつかずにいる。さらに今年は、フランスの会社でも働くことができる、10年ビザの申請が通ってしまった。今後も「そろそろ帰国かな」と言いつつ、この街に住み続ける気がする。
(イラスト/題字 山本アマネ)